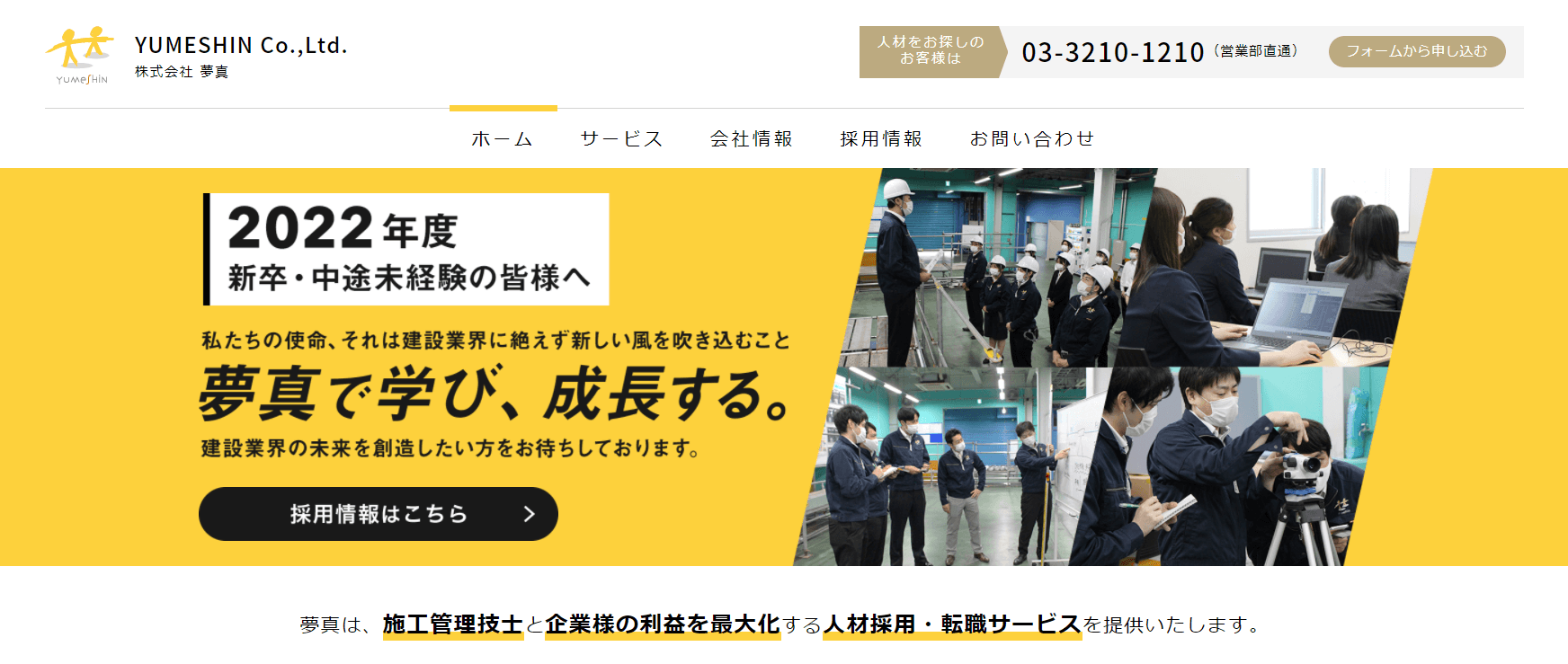建設業務は派遣禁止ってホント?禁止されている理由も解説!

建設業務はその業務の特殊性から、一部の例外を除き、労働者派遣事業の適用除外業務とされています。違反した場合の罰則もあるので、注意しておきたいところです。ここでは建設業務で派遣が違法となるケース、その理由、また違反したときの罰則について紹介します。しっかり把握しておきましょう。

〒260-0014
千葉県千葉市中央区本千葉町1-1 日土地千葉中央ビル9F

〒106-6135
東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー35F

〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-4-1 丸の内永楽ビルディング22F

〒450-6425
愛知県名古屋市中村区名駅三丁目28番12号 大名古屋ビルヂング25F

〒100-0005
東京都千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館17F
業界で派遣が違法となるケースがある
では早速、元となる法律を紹介します。労働者派遣法4条1項2号では、労働者派遣事業を行ってはならない対象として、建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう)となっています。この禁止対象に当てはまってしまえば、違法なことをしているつもりはなくても、違法とされる可能性があるので注意が必要です。
「自分が相手先としている契約は派遣契約ではなく、請負契約なので大丈夫」と考えている方も要注意です。指揮命令関係を生じないのが請負契約ですが、実際には発注者が請負先に指揮命令をしていることがあります。そして契約形態によらず、実態にあわせて労働者派遣、請負のいずれに該当するかが判断されることが、厚生労働省によって示されているからです。
「そんなつもりではなかった」ということにならないように状況と法律、指針などをしっかり確認しておきましょう。ただ、どこまでの助言が指揮命令とされるかの線引きが難しいこともあるでしょう。
迷ったら経済産業省の「企業実証特例制度・グレーゾーン解消制度」を活用してください。これはズバリ、事業者が現行の規制の適用範囲が不明確な場合においても安心して新事業活動を行えるように、具体的な事業計画に応じて、あらかじめ規制の適用の有無を確認できる制度です。
ただしいくつか注意点もあります。新事業活動を行う者が事前相談をした場合を対象としているため、事業が開始している場合は、対応してもらえない可能性が高いです。また回答の通知は原則として1か月以内ですが、延長されることがあります。便利な制度なので活用していきましょう。
業界で派遣が禁止されているのはなぜか
建設業特有の理由により派遣が禁止されています。主な理由を3つ紹介します。
重層的な下請け関係に悪影響を及ぼすから
現在建設業務では、とくに大きな案件では、重層的な下請け関係、つまり孫請けやひ孫請け等の請負関係が生じることが多いです。それぞれの請負関係の中で、雇用者に指揮命令する者や、多種多様な専門職の職人さんが働いています。
たとえば大工さん、左官屋さん、水道屋さん、電気工事屋さんなど、複雑な状態となっています。さらに、このなかに労働者派遣事業というシステムを導入すると、請負関係と派遣関係が混在するため、雇用に悪影響をおよぼしてしまう、というのが1つ目の理由です。
建設業務労働者就業機会確保事業制度が存在するから
2つ目の理由として、建設業の事業主が自己の常時雇用する建設業務労働者を、ほかの事業主に一時的に送り出す、建設業務労働者就業機会確保事業制度が設けられているからです。
この制度によって建設業務労働者は、不安定になりやすい派遣労働者になることなく、閑散期に他の事業主の仕事ができます。建設業務労働者は送出事業主とは雇用関係に、受入事業主とは指揮命令関係となります。雇用の安定を図る制度です。
建設業務労働者就業機会確保事業制度とは
実施計画の認定を受けた事業主団体の構成事業主が、自社で雇用している労働者を、同じ事業主団体に所属する他の構成事業主の建設業務に一時的に送り出す制度です。この際、労働者は元の会社との雇用関係を維持したまま、送り出し先の事業主の指揮命令を受けます。
引用元:厚生労働省ホームページ『建設業務労働者就業機会確保事業』
建設業務有料職業紹介事業制度が設置されているから
3つ目の理由です。この制度は「事業主団体が、その構成員を求人者とし、又はその構成員若しくは構成員に常時雇用されている者を求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における建設業務に就く職業に係る履用関係の成立をあっせんすることを有料で業として行うこと」と定義されています。このあっせん業によって、雇用の安定化と流動化の両立を図っています。
建設業務有料職業紹介事業とは
実施計画の認定を受けた事業主団体が、「職を求める労働者」と「労働力を必要とする事業主」を有料でマッチングさせる制度です。ただし契約期間が定められる派遣と違い「期間の定めのない労働契約」が対象となります。
派遣を雇うとどんな罰則が科せられるのか
労働者派遣法により、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されるようです(同法59条)。ほかに業務改善命令や業務停止命令を受けます(同法49条)。この命令は派遣先だけでなく、派遣元企業にも労働者派遣の停止命令がなされます。そしてこれらの命令に違反した者は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されるようです(同法60条)。
建設業界は請負契約が普通で、重層的な下請け関係など業界特有の事情があり、派遣が禁止されています。その代わりに建設業務労働者就業機会確保事業制度、建設業務有料職業紹介事業制度といった特有の制度があり、労働者を保護しています。
今回紹介した、建設業界の派遣禁止理由、建設業界で派遣かどうか判断に迷ったときの対応、派遣を雇った場合の罰則などに注意して、グレーゾーン解消制度なども活用し、知らないうちに法律違反とならないように活動していきましょう。
建設業における派遣の適正な運用のためのガイドライン
労働者派遣とは
人材不足が深刻化している建設業ですが、人手が増えない理由のひとつに「労働者派遣の禁止」が挙げられます。派遣会社は、さまざまな業種・職種で働けるほか、ライフスタイルに合わせて選べるのがメリットです。
また派遣会社のサポートも受けられるので、正社員に比べて無理がありません。会社側にとっても、即戦力の確保やコスト削減につながるため、派遣の導入は人材不足を解消するうえで非常に役に立つでしょう。
しかし、建設業においては派遣の適用が禁止されています。その理由については後述しますが、場合によっては罰則もあるので、建設業を希望している方は気をつけましょう。
派遣が禁止の理由
建設業で派遣が禁止されている理由は、主に2つあります。
1つ目は、建設労働者の安全確保です。建設業は、元請け会社のほかに、下請けや孫請けなどが存在します。会社によってさまざまな雇用があるため、そこに派遣が加わってしまうと、労働災害のリスクが高まります。
そもそも派遣会社は、ご存知のとおり派遣元と雇用契約を結んで派遣先で働きます。建設業に直接雇用されていないので、指揮命令系統が曖昧になりやすく、万が一トラブルが遭った場合にきちんと対処してもらえません。不利益を被ることになりかねないため、安全を確保するために派遣の採用を行っていないのです。
2つ目は、不安定な雇用の防止です。建設業は、基本的に「受注生産」になります。受注を受けてから業務に取りかかるため、ほかの業種に比べて労働者の需要が不安定です。そんな状態で派遣を認めてしまうと、受注が少ない時期に派遣切りにあってしまう労働者が大量発生してしまいます。
ようするに、仕事を失う危険性があるというわけです。こういった不安定な雇用を防ぐために、建設業は派遣の活用を禁止しています。
一方で「建設業務有料職業紹介事業」や「建設業務労働者就業機会確保事業」などの制度が利用できます。
罰則
もし違反をしてしまった場合、派遣元と派遣先に罰則が科されます。「知らなかった」では済まないので、建設業で募集を行う際は十分気をつけましょう。
まず、派遣元には1年以下の懲役または100万円以下の罰金を支払うことになります。それに加え、事業停止が命令されます。
もちろん、派遣先にも「是正勧告」が出されることになるので、きちんと従わなければいけません。万が一無視した場合、ペナルティ(企業名の公表)が与えられるので注意してください。
派遣を活用するには
基本的に建設業は派遣の活用がNGですが、すべての業務が禁止されているわけではありません。ここでは、派遣が活用できるケースとできないケースを紹介します。
適用除外の業務
労働者派遣が適用除外になる業務は、土木や建築をはじめ、工作物の建設や改造、修理、変更、解体業などが挙げられます。また、これらの作業を準備する業務においても適用外になります。
もう少し詳しく説明すると、ビル・家屋などで資材の運搬・組み立てや建築・土木工事現場内での資材・機材の配送、壁や天井・床の塗装・補修などです。これらは「一般社団法人日本人材派遣協会」の「建設業務」で確認できます。
イベントの大型仮設テントや仮設住宅(プレハブ住宅など)も、派遣の活用が認められていません。
適用される業務
一方で、派遣の活用が認められている建設業は、事務作業・CAD/BIM/CIMオペレーター・施工管理業務などが挙げられます。建設業にはいろんな業務があり、土木や建築だけではありません。ようするに、直接作業に関わらない業務であれば、派遣を活用しても問題ありません。
たとえば事務作業は、その名のとおりオフィス内で電話対応や書類整理などを行います。ただし、工事現場での作業を兼ねている場合は、軽度のものでも適用外になるので注意してください。
オペレーターに関しては、工事現場での作業はないため、全般的に派遣の活用が可能です。施工管理業務は、事務作業と同様に工事現場の作業を兼ねている場合は派遣NGとなります。
【建設業】おすすめ人材派遣会社ランキングTOP3
- 未経験者や建設業界経験の浅い方
- 実践的な教育研修を受けたい方
- 働きながら様々な資格等を取得したい方